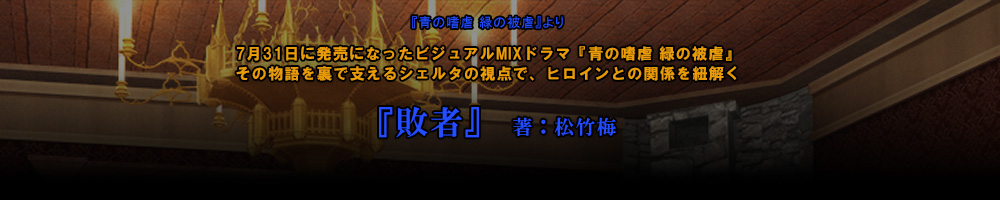 |
|
指先を添えた盤上の駒が温い。たぶんティータイムから夕刻まで直射日光にさらされていたせいだろう。つまりそれほど長く、私は対面に座す女性――私の愛してやまない人と盤上遊戯に興じているのだ。
もう数百回敗退しているのに、彼女は懲りずに挑戦してくる。負けず嫌いもここまでくると物好きの域に達するのではないだろうか。
吐息に紛れさせて苦笑した私は、かくいう私こそが物好きかと内心で自嘲した。瀟洒なつくりの窓際に目先を移せば、そこから飛び去る鳥たちの同意する声が空気を震わせた。元同類なだけあって、かしましい彼らは私に容赦ない。
鼻を鳴らし、心の中で答える。
(放っておいてください。あと少しなんですよ……、たぶんね)
叶わない恋という戦いに破れ、めげずに挑むこと早十年。腐るほどの愛の睦言という砲弾を打ちこみ続けた相手は、しかし籠城戦の構えを一向に崩さない。兵糧が尽きたこちらのほうが精神的に参ってきそうだ。
がっちりと守りが固められた駒の配置を見て、やれやれと首を振る。
「貴女の守りは、その唇のようにかたい」
「失礼ね。毎日美容に良い香油を塗っているのよ」
「感触の話ではなく、私を迎え入れる気概のことですよ。いつまで経っても、貴女は唇を開けて待っていてくれない。普通の乙女は、この顔が近づけられればうっとりとして唇を綻ばせてくれるものなんですが」
「普通の反応がほしければ、普通の女のところに行きなさい」
「嫌ですよ。そんなのつまらない」
「ではこの硬い唇で我慢するしかないわね」
「私の舌を喜んで迎え入れてくれる日は永遠にこないと?」
「もしそんな日がくるとしたら、それは貴方が負ける時よ、シェルタ」
「なぜ?」
「貴方の前で口を開けたままの間抜け顔を晒すとしたら、私がこの盤上遊戯で勝利して、笑いが止まらない時でしょうから」
「なるほど。しかし勝利に酔いしれる貴女の顔も見てみたいものです。きっととても可愛いのでしょうね」
「……背を向けて笑うことにするわ」
遊びに聞こえているのであろう言葉が全て私の本心だと知ったら、彼女はどんな顔をするのだろう。
こんなにも長い時をかけて口説いたのは初めてだから、予想ができなくて不安な反面、胸が躍る。
トントンと指先で机上を叩く動作をしてしまったのは、らしくもなく高揚しているせいだ。
音につられ、彼女の視線が私の手元を見る。おそらく、私が何か特別な作戦を立てていると思ったのだろう。
警戒心を滲ませた目に曖昧な笑みで返し、翻した手で先を促した。
(ああ、早くその駒を動かして。そしてこの籠城戦を、終わらせてください)
夕刻の光で赤々と染められた盤上は、まさしく炎に巻かれた戦場の様相を呈してる。
彼女が守る女王の駒と、私が動かす騎士。同じ炎で焼かれていることに不思議な安堵をおぼえて微笑むと、彼女がますます怪訝そうに眉を顰めた。
「安心するにはまだ早いわよ」
「いえ、そういう意味ではなかったのですが……まあ、どちらにしろ同じことですね」
「何を言って……」
「かくして女王の身柄は遊び人の騎士に奪われた」
反応を楽しむべく途中で声を遮り、摘まんでいた手駒を彼女のそれに軽くぶつける。
コロリと転がった哀れな騎を見て、彼女の顔はさっと青ざめた。かと思うと、ふるふると身を震わせ、次第に耳まで赤くなっていく。悔しくてたまらないといった様子だ。
「まだ続けます?」
小首を傾げて問うと、隠しもしないむっとした表情が返される。
賢い彼女は、この先どう続けても負けしかないのを悟ったらしい。大仰な溜息をついて椅子から立ちあがると、私の前までつかつかと歩みよってきた。
彼女が負けたら私に口づけを捧げるという、もはや二人の間では定番になっている約束事を、律儀に果たしにきたのだろう。
「さあ、勝者の権利を受けとりなさい」
敗者にしてはだいぶ偉そうな態度で言う彼女の、少し子供っぽく尖らせた唇が可愛らしい。それがゆっくりとした動作で重ねられようとした瞬間、私は喜びのあまり吐息を揺らし、心からの笑みを浮かべた。心臓が爆ぜそうに高鳴っている。
常とは違う反応を訝しんだ彼女が口を開く前に、私は目前の柔らかな唇に指先を添えて囁いた。いや、興奮しすぎて声が掠れたといったほうが正しい。
「私の、勝ちだ」
「? ええ、そうね」
「私の勝ちなんですよ」
夕陽に透かされた瞳が、困惑に揺れる。
意図するところが全くわからないといった顔を見ていると多少傷つきもしたが、まあ仕方ない。本人が忘れるほど遠い過去の話なのだから。
私は興奮で吐けずにいた息を少しずつ漏らし、高らかに宣言する。
見ろ、これが執念の賜物だ。
「――貴女は十年前、私に約束した。十年間愛を囁き、千回この盤上遊戯で勝利すれば、私の妻になってくれると。今日がその十年目で、千回目の勝利です」
「……!」
普段は強い意志を湛える双眸が、これ以上ないくらい瞠られる。
こぼれ落ちそうな瞳を受けとめるように頬を撫で、立ちあがると同時に細い腰を引きよせた。
敵兵に迫られても怯まない華奢な肩が、びくんと跳ねる。視線は右に左にと忙しなく動き、明かな動揺を訴えていた。
それらが段々と落ちついてくるのを待って、そっと問いを重ねた。
「約束、守ってくれますよね?」
「貴方……、本気で……?」
恐らくその問いには、いくつもの意味が込められているのだろう。
本気で約束したのか。
本気で十年間も愛していたのか。
――未だ微かに揺れている瞳の奥が何度も確認してくるから、私は頷いて肯定した。
「私以上に貴女を愛せる人はいないと断言できる」
「……私と結婚しても、貴方は幸せにはなれないわ」
「それは私が決めることです。貴女が判断することではない」
強く言い切れば、彼女は息を飲み、唇を噛む。
私は仕上げとばかりに彼女の耳元に唇を寄せ、想いの丈を吹きこんだ。
「それに私の執念深さは、貴女もよく知っているでしょう。火の中でも、海の上でも、貴女がいるところに私は駆けつける」
「……、そうだったわね。貴方は、本当にそうだった」
深く嘆息した彼女は、諦めとも納得ともとれる表情を作る。どこか遠い目になったのは、この十年で積みあげられた私の『実績』を数えているからだろう。
「あれは五年前だったかしら。海向こうの蛮族が押し寄せてきた時、誰もが撤退を勧める中で、貴方は私と共に砦に残った」
「ええ、どこかの頑固な淑女が動こうとしなかったので」
「海岸を死守しろとの女王陛下のご命令に背くわけにはいかないでしょう。それに私の土地を傷つけられるのは癪に障った」
「けれど、貴女自らが出向くことはなかったでしょうに」
「そういう貴方こそ、私の代わりに射られることはなかったでしょうに」
同じ調子で返され、わざとらしく片眉をあげる。
「まったく……、回復したから良かったのの、後遺症が残ったらどうするつもりだったの」
「貴女の同情を引いて、結婚を迫っていたと思いますよ。ああ、なんだ、そうしていれば早く決着がついたのに……しくじりました」
言葉遊びに応じる偽りの余裕を見せると、彼女はまた深々とした溜息をこぼし、私の肩に額を乗せた。
なんてことない仕草だが、彼女がすると大きな意味を持つ。頑として誰にも寄りかからなかった彼女が、初めて自らの意思で体重を預けてくれたのだ。
上着越しにじんわとした熱が伝ってきて、うっかり涙を流しそうになる。
私が泣きそうになっているなど、彼女はきっと想像もできないだろう。
案の定、私の態度を批難する――しかしどう聞いても可愛く拗ねているような声が聞こえてきた。
「貴方はいつも余裕で、遠慮もせずに、私の心に踏み入ってきた。まさか十年も付きまとってくるなんて、出会った頃は予想だにしていなかったわ」
「付きまとうとは、酷いですね。私は貴女のいい悪友だったでしょう?」
「悪友と自称する時点で、良くはないわよ」
「しかしそんな男を、貴女は愛してしまった」
臆せず口にした言葉に、彼女の体が強ばる。
私は少し身を引いて細い顎に指を添えると、優しく持ちあげるようにして顔を覗きこんだ。
強引に視線を合わされ、先ほど以上に彼女の瞳の奥が揺れる。
「ずいぶんと自信があるのね」
「貴女のことなら、なんでも知っていますから。けれど貴女の口から言われなければ、それはなんの意味もない」
「っ……」
「教えてください。私を、どう思っていますか」
「……貴方への気持ちを語ることは、私にとっては戦で百万人殺すよりも罪深い行いなのよ」
「ええ、知っていますよ。忌々しくなるほどにね」
「とても求婚の言葉とは思えないわ」
「普通の求婚の言葉など、貴女には似合わない」
形の良い眉が苦しげに寄せられる。唇は小刻みに震え、瞳は乙女のごとく涙で潤んでいた。いよいよ追いつめられたと悟った顔だ。
勝利を確信した私は、歌いたい気分で駄目押しをした。
「さあ、観念して答えてください。たとえこの場から逃げたとしても、私はどこまでも貴女を追いかけ、付きまとい、全力で愛します」
言い切った直後、彼女が恐れるように息を飲んだ。
反射的に逃げようとする華奢な体を、有無を言わさない力で引き寄せる。
口づけを予感させるほどに顔を近づければ、最初は動揺に揺れていた瞳が、私の言葉が導く通りに――妙な陰が過ぎった気がしたが――観念していくのが見えた。
壁時計の秒針が何周したかは憶えていない。
私にとっては永遠にも思える沈黙を経て、涙声にも聞こえる声が答えた。
「……貴方を愛しているの、シェルタ」
渇望して、外堀を埋めて、すっかり予想の範囲内になった返答。
けれどその音が耳に入った瞬間、ぶるりと全身が震えた。酷い寒気にも似た強烈な感覚が背筋を駆けぬけ、次いで湯船に浸かった時のように体温が上がる。
鼻の奥がツンとするのは、たぶん久しぶりに本気で泣きそうだからだ。
(もうすっかり、涙など枯れ果てたと思っていたのに)
しかし喜びの涙ならばいくらでも溢れるらしい。
息を吸いこめば「う、く」と情けない呼吸音になりそうで、私はなんとか我慢した。
まだ、泣いてはだめだ。結婚式を挙げるまでが勝負だ。
そう自分に言い聞かせ、勢いよく溢れようとする涙を、用心深く再開した深呼吸で制した。
「シェルタ?」
せっかくの告白に何の返答もないから、不安に思ったのだろう。私の眼下で女神のごとき美貌が悲しげに曇る。
私は誤解させてしまったことに焦りを感じつつ、意識して口元から力を抜いた。
ここは、気が遠くなるほど待って手に入れた晴れの舞台。第一声で噛むという格好悪い失態は犯せない。
「その言葉を、ずっと待っていました」
やっと手に入れた人が逃げてしまわないよう、恐る恐る、彼女の頬に触れる。
(彼女の頬は、こんなにも柔らかかっただろうか。吸いこまれてしまいそうだ)
過ぎる歓喜は、五感をおかしくさせるらしい。ちりちりと指先が炙られているのではないかと思うほど、全身が熱く火照っているのを感じた。
「やはり貴方は、いつだって余裕なのね」
「私の、どこが?」
甚だ疑問だ。今まさに発狂しそうなほどの歓喜に飲まれているというのに、一体どこに余裕を見い出されたのだろうか。
そんな正直な気持ちを反映した表情も、十年間私の下手くそな微笑を見続けた彼女には、芝居だと受け取られてしまったようだ。少し拗ねたふうに顔を背け、ぼそりと呟く。
「今だって、こんな焦らすみたいに私に触れる」
「じらす……?」
音をなぞり、一拍遅れて意味を理解する。途端、あまりにも見当違いな判断がおかしくなって、つい声をあげて笑ってしまった。
ますます拗ねたふうに尖る唇が可愛らしい。怒った時に眉間に寄る皴は年齢のせいで濃くなったけれど、それもまた可愛い。目じりの小さな皺も、愛おしい。つまり全てが可愛くて愛しくて大切だ。
心の中が「愛している」で溢れ、わからせてやりたいという衝動がわきあがる。
半ば諦めている、どうせ無理だと言いながら、それでも執着して、みっともなく縋りついて――やっと成就した恋。私がどれほどこの瞬間を待ちわびていたのか、直接体に注ぎこんで教えたかった。
「……焦らされていたのは、私のほうだ」
え、という彼女の短い声ごと飲みこむ勢いで唇を奪う。そうなってしまったら、もう啄むなんて余裕のある動きはできなかった。高ぶりすぎて眩暈がする。気持ちが急く。一刻も早く彼女の中に触れたくて、やや強引に口内に舌を差しいれた。また焦らしているなどと思われてはたまらないから、両手でしっかりと頬を押さえ、逃がすつもりはないのだと全身で告げる。
「待っ……、んぅ! はっ……、いそぎ、すぎ」
「愛しています」
「っ、あ……、シェル、タ」
彼女の口端からこぼれる唾液がもったいなくて、荒々しい口づけの合間に舌先で舐めとる。その度に「愛しています」「私の女神」と囁き、自分で聴いていてもうんざりするくらいの甘ったるい声で囁いた。
舌と舌を擦りあわせるだけの単純な接触が、信じられないほど心地よい。大きな幸福感を生む。口づけどころか幾度も体を重ねたはずなのに、今が一番繋がっている気がした。
「んっ、ふ……ぁ、はぁ……っ」
「なんでこんなに、貴女の唇は、舌は、甘いのでしょう」
「甘くなんて……、っ」
顔の向きを入れかえる際、あまりの感動で内心の声が口からこぼれてしまった。
律儀に答えようとした彼女の舌を夢中で吸いあげれば、涙で潤んだ瞳に抗議の色が浮かぶ。
たぶん息苦しいのだとわかったのに、やめてあげることができなくて申し訳ないなと、恋に蕩けた頭の片隅で思った。思っても、やめられなかったのだけれど。
「は、少し……疲れてきた?」
「っ、わかっているのなら、いい加減はな……、んぅ!」
長すぎる口づけで疲れてきたのであろう舌を捕え、さらに追い立てる強さで捏ねまわす。根本、柔らかい裏のほう、僅かな凹凸を感じる表面を、じっくりと舐めて味わった。
くちゅくちゅと音が立って、つい彼女を抱いている時を連想してしまう。腰まわりに血が集まってくる。
(いや、明日は大事な式があるのだから、今夜は抑えないとだめだ。せめて三回くらいにしよう。ああ、本当に……今すぐ彼女を抱えて、式場に走っていきたい)
思いだしたように胸に湧いた願いで、僅かに理性が戻る。しかし冷静になったのかというとそうではなく、鼓動はいっそう早くなり、胸がはち切れそうだった。素晴らしい未来の数々が、私の余裕を根こそぎ奪っていく。
はあ、とようやく息をした彼女には悪いが、考える暇は与えてやれない。
あらん限りの力で、精一杯の誘惑の声を出した。
「明日、式を挙げましょう。準備は万端ですから、全て私に任せてください」
「ずいぶんと急な話ね。外堀を埋められている気分だわ」
「いけませんか」
「……いいえ。私は世界で一番幸せな花嫁よ」
ふわと花が綻ぶような笑顔だった。他の男に向ける蠱惑的な微笑も素敵だが、この笑顔が一番美しい。見ているだけで泣けてくる。
酷い不意打ちをくらった気分と、それ以上の幸福感を噛みしめ、ほぼ無意識に呻いた。
「っ、あまり煽らないでください。抑えられなくなる」
「え?」
「まったく、私が何万……いえ、何年我慢したと思っているのですか。無自覚な妻には、おしおきが必要ですね」
なんのことだと困惑をあらわにする眉間に、ちゅっと軽く音をたてて口づける。
もう一度唇が触れたら我慢ができなくなって、そのまま抱きあげると、柔らかな寝台へと直行した。
「明日式で立てなくなっても、文句は言わないでくださいね。こんなに可愛い貴女がいけなのですよ」
早速の抗議を紡ごうとした舌を吸いあげる。
官能的な吐息を漏らした彼女の瞳の奥が、また一瞬だけ不可解な陰を宿したように見えたが、幸せ気分に酔いしれた私の情熱を削ぐことはできなかった。
翌朝、指輪などの贈り物を運んできた私は、天にも昇る気持ちで屋敷の廊下を歩いていた。
「愛しー、愛されー、私たちはー」
この国には結婚式では定番の愛の歌がある。聞く度に反吐が出ると思っていたが、今思えばあれは全て幸せになっていく者たちへの嫉妬だったのだろう。
だって、今はこんなにも高らかに歌える。少し前の私が見たら額を押さえて「やれやれ」と嘆息しそうなものだが、死ぬほど我慢したのだから今日くらいは羽目を外してもいいはずだ。
そう自分に言い訳をしつつ、扉の前に立つ。彼女がこの向こうで綺麗な花嫁衣装を身に纏っていると思うと、見る前から感動でむせび泣きそうだった。
(ついに、ついに、ついに……! 彼女が私の花嫁になった!)
喜びのあまりぶるぶると震える腕を動かし、思い切きって扉の取っ手を回す。直後にノックを忘れたと気がついたが、興奮しすぎて勢いを止められない。開き直って、一息に踏みこんだ。
「私の可愛い花嫁、準備はできましたか?」
きっと彼女は、私の浮かれっぷりに呆れて――
「……?」
室内に入った瞬間、まず違和感をおぼえた。
彼女は婚礼衣装を着ているが、寝台に横になっている。扉が開けられた音にも、私の浮かれ声にも、無反応だ。
昨夜激しくしすぎて疲れさせてしまったのだろうかと心配になり、同時に……そわりと落ちつかない気分になった。
「そろそろ起きないと、式に遅れてしまいますよ」
苦笑しながら近づいてみても、やはり彼女は瞼を閉ざしたまま。
それならばと物語の王子よろしく口づけで起こそうとした。
そして、気がつく――
「息を………………」
して、いない。彼女は、息をしていなかった。
「え……。え……?」
なにがなんだかわからなくて、間の抜けた声が出る。
現状把握ができないなど未だかつてなかったことだが、とにかく頭が上手く回らない。瞬きの一つもできず、瞠った目に彼女の美しい顔を映していた。
昨夜、私の愛の囁きによって染まっていた頬は、異様に白い。唇は口づけをねだるように薄く開いたままだったが、吐息をこぼさない隙間は、虚ろで恐ろしいものに見えた。
数十秒呆然とし、窓の外でバタバタと鳥が羽ばたく音で我に返る。私は未だ収集がつかない思考回路をまとめ、とにかく蘇生措置をしなければいけないと気を立て直した。
「まずは、原因……。原因を、探らないと……」
どっ、どっ、と心臓がうるさく跳ねている。ふきでた汗が額を伝い、せっかくの婚礼衣装を濡らした。
「探ら……、ないと……?」
動揺でなかなか定まらなかった視点が、ある一点で留まる。
探るまでもなく、原因は私のすぐ目の前にあったのだ。
「これは……」
敷布の上に、コロリと転がっている小瓶。力の入らない手でなんとか拾い、その瓶の口を鼻先に近づけた。……本当は見つけた時点で、なんの臭いかわかっていたのに。
「ど……く?」
忌々しいほどに優れたこの身は、こんな時でも力を発揮してしまう。瞬時に瓶から漂ってくるものと、彼女の口元に残る臭いが同じであるとわかり、いっそう混乱をきたした。
これは、猛毒だ。悶え苦しむことはないが、飲めば数秒と待たない内に眠りに落ちて、そのまま死ぬ。
「なぜ……?」
限界まで嗅覚を研ぎ澄ませるが、他の者が入ってきた痕跡はない。つまりは……
「貴女が、自分の意思で飲んだのか……?」
自分で出した結論が信じられない。また呆然と立ち尽くす。
優れているはずの五感は途端に麻痺して、遠くから聞こえてくる鐘の音色も意識を上滑りしていった。
一体どのくらい、そうしていたのか。唐突に力が抜けて、立っていられなくなった。かくんと情けなく膝を折り、彼女の脇に腰を落とす。
「なぜ……」
あんなに、愛を囁きあったではないか。
最初は怒るというよりも、ただただ目の前の事実が受け入れられなくて、意味もなく首を振った。
次第に手先が震えだし、それが全身に広がって、ますます視界を揺らす。平衡感覚も狂い、臓腑が痙攣し続けた。
「ぅ……、あ……」
吐き気に悶えて敷布を握りしめれば、ふつふつとした激しい怒りが込みあげてきて、その感情のままに布を引き裂いた。
「なぜだっ!?」
ひた隠しにしてきた爪も、牙も出して、ありとあらゆるものを切り裂く。
上等な羽毛が舞いあがり、室内が雪の日のように白くなった。
もう何も見たくない。このまま全てが覆いつくされて何も見えなくなればいいのにと願ったが、壊せるところがなくなると、最終的にはどうしても無傷な彼女に目がいってしまう。
絶対に傷つけたくないのに、どうしても怒りを叩きつけたくなって、ギリギリと彼女の細い肩を掴んだ。それでも衝動が収まらず、鋭い牙を柔い首筋に突き立てようとして……
「っ、……なぜ?」
嗚咽と共に、涙がぼろりとこぼれた。
幾度目かわからない問いかけが、白く染まった室内に霧散する。
忍び寄ってきた虚しさに足をとられ、私は再び彼女の横に腰を落とした。
「……そんなに、か」
そんなに、この顔とは幸せになれないのか。
問いかけたかったけれど、答える者はもういない。彼女の心は深く閉ざされ、私に関する一切を拒んでいた。
本当は、今すぐにでも彼女を生き返らせたい。けれど他でもない彼女が、生きることを望んでいないのだ。だから私は……、もうこの世界では力を出せない。
「ああ……」
ふと、昨夜の彼女の瞳を思いだす。あの妙な陰を、観念ゆえのものだと思っていたが、それはある意味正しく、また間違ってもいたのだろう。
「貴女は観念して、私の妻になったのではなかったんですね。観念して、過去と向きあうことを放棄したのか。私ごと、苦しみや罪悪感を捨てたのか」
ぼそりぼそりと呟いて、物言わぬ愛しい人を見つめる。
動揺、否定、怒り――その果てに辿りついたのは、ただの『無』だった。心が空っぽだ。指一本動かす気になれない。
わぁんと、頭痛を伴う耳鳴りが止まらなかった。
「こんなにうまくいっていたのは、はじめてだったんだ……。何万回とやり直して、これで最後だと思っていたんだ……」
だから、さすがに……心が折れた。ぽっきりと。
脱力したまま、ぼんやり彼女の唇を眺めていると、徐々に色を失っていくのがわかった。絶対に動きたくないと思っていたのに、それだけは残念に思えて……、霞みがかかった意識のまま腕を伸ばした。
そうして、優しく優しく抱きあげた。
「愛しています」
冷たくなった額に唇を押しあて、昨夜の彼女を脳裏に描きながら微笑む。
私を愛していると泣きながら言った彼女の声が、耳の奥でこだまする。
「さあ、結婚式にいきましょう」
もはや何の意味もない誓いの儀式だが、この地獄について考えるのが嫌で、とにかく違うことで頭の中を満たしたかった。
教会へと運ぶ間、なぜだか無性におかしくなってきて、結婚式では定番の聖歌を口ずさむ。
「愛し、愛され、私たちは……」
歌いながら、雲の上を歩く心地で祭壇の前に辿りつく。
天井の色ガラスが無駄に綺麗だ。
ゆっくりと膝を折り、用意していた指輪を取りだした。
「見てください。この日のために、十年かけて選んだんですよ」
一人きりの宣誓。一人きりの指輪交換。
無理矢理伸ばした彼女の指はポキリと不気味な音を立てる。
この壊れた結婚式そのものだ。
「さあ、次は……。次は……。…………」
動けない。
ここから先、どうすればいいのか。
途方に暮れて彼女の顔を眺める内、そういえばと思いだす。
「誓いの口づけが、まだでしたね」
上手に口づけようとしたのだけれど、ぽっかりと開いたままになった彼女の口は、顎下に手を添えていないと閉じられなくて、どうにも様にならない。
仕方なく諦めて、誓いの証にしては淫らかと思いながら、深い口づけをした。
いつもなら応えてくれるはずの舌が引っこんだままで、当然だと理解しつつも違和感に苛まれる。それを消したくて、執拗に粘膜を舐め、啜った。
苦い毒と一緒に、彼女の願いを汲みあげる。もう幾度となく、繰り返してきたように。
そして彼女の最後の記憶に触れた私は、全てを理解した。
「貴女は……本当に勝手な人だ。あんなにも愛を囁いておきながら、私を傷つける前に戻りたいなどと願うのか。全て、なかったことにするのか」
りぃん、ごぉん。と、幕引きを告げる教会の鐘の音がやかましく鳴り響く。
無遠慮な祝福に脳内をかき混ぜられて世界が揺らいだ。
「くっ、ははっ……あはは、……あはははは……くくくっ」
すさまじい吐き気で鳩尾のあたりがひきつれる。それでいて愉快でたまらず、くつくつと喉を鳴らして笑い続けた。
やがて辺りが静まり返った頃、笑みの形になったままの唇を、彼女の半開きになった口に押し当てた。
もう、涙は一粒も出なかった。
離れると同時にあることが脳裏を過り、また笑う。
――本当に皮肉だ。口を開けて待っていてくれることを望み続けた結果、こんな形で叶ってしまった。
「ああ、貴女の言う通り、私の『負け』だ」
何千、何万とこの恋が破れて……私はようやく、敗者であると自覚した。
【あとがき】BY松竹梅
皆さんは、青緑のどのキャラがお気に入りになりましたか?
私はもちろん全キャラなのですが、どこがお気に入りなのかと問われれば、彼らのどこか欠けていたり醜い部分なのかもしれないなと思います。
さて、次回からは全年齢対象の女性向けゲーム
『罪喰い〜千の呪い、千の祈り〜』の特集が始まります!
こちらも全力でとりかかっておりますので、是非チェックしていってください。
|
|
|